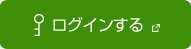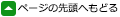テーマ別関連資料の紹介
伴林光平(ともばやし みつひら)
幕末に活躍した志士であり、国学者、歌人でもある伴林光平は、成法寺村(現在の南本町)の教恩寺の住職であった八尾市ゆかりの人物です。
光平は、1813年志紀郡林村(現在の藤井寺市)の真宗尊光寺に生まれ、長じて京都、大和で仏教の修行に励みます。さらにその後、朱子学・国学・和歌を学ぶために和歌山や江戸など日本各地を転々とする生活がつづきました。
1845年教恩寺の住職として八尾に落ち着いた時には、光平は33歳になっていました。僧侶としての仕事より和歌や国学の研究、講義に熱心であったようで、歌会を催しては地元の人々に和歌を教えるほか、顕証寺や大信寺などで歌道指南役をつとめました。国学の分野においては、とりわけ大和・河内の山稜調査に心血を注ぎ『大和國陵墓検考』など数多くの著書を執筆しました。一方、尊皇攘夷運動の盛り上がりの中で、光平も国学者としての立場から、志士たちに同調し行動をともにしていました。そしてついに1861年、尊皇思想にその身をささげるべく還俗する意思を固め、寺の壁に決意をこめた七言絶句を残し、16年間を過ごした八尾を去ったのです。
大和に移り住んだ光平は、過激派志士とともに討幕をめざして奔走しました。1863年、公家の中山忠光を盟主とした一団が挙兵すると、光平も記録係として彼らに加わります。しかし、天誅組とよばれた彼らの義挙は失敗に終わりました。捕らえられた光平は翌年処刑され、獄中で挙兵の経緯を追想した『南山踏雲録』が最後の著書となりました。
資料(書名のアイウエオ順)
| 書名 | 著者(編者) | 出版者(出版社) | 出版年 |
|---|---|---|---|
| 河内長野市史 第2巻 本文編 近世 | 河内長野市史編修委員会 | 河内長野市 | 1998 |
| 天誅組紀行 | 吉見良三 | 人文書院 | 1993 |
| 伴林光平「真筆南山踏雲録」の成立 上 (大阪春秋106) |
鈴木純孝 | 大阪春秋社 | 2002 |
| 伴林光平と八尾西岡家遺稿 (河内どんこう74) |
鈴木純孝 | 八尾文化協会 | 2004 |
| 伴林光平の研究 | 鈴木純孝 | 講談社出版 サービスセンター |
2001 |
| 南山踏雲録 | 保田與重郎 | 新学社 | 2000 |
| 八尾市史 前近代 本文編 | 八尾市史編集委員会 | 八尾市 | 1988 |